少子高齢化と人口減少が加速する地方において、自動車整備事業の継続は喫緊の課題である。こうした危機感の中、鳥取県琴浦町の地元自動車整備業者5社が手を組み結成された琴浦モビリティグループ(コトモビ)の取り組みが、全国のアフターマーケット業界関係者から注目を集めている。コトモビは、単なる共同事業に留まらず、「協力」「共有」「分担」を理念に掲げ、地域社会のライフラインとしての自動車モビリティを確保すると同時に、電子制御装置整備といった高難度分野への戦略的な事業継承を成功させている点が革新的である。その先進的な実践は、「クルマ・社会・パートナーシップ大賞」地域・コミュニティ活性化賞を受賞するなど、縮小市場における持続可能なビジネスモデルとして、全国に波及効果をもたらす可能性を秘めている。
地域の危機を乗り越える連携体制
コトモビは2020年(令和2年)に発足。地方では公共交通機関の撤退が進み、大手ディーラーの店舗再編成によるサービス体制の脆弱化が進む中、自動車が「ライフライン」である同町において、5社の経営者が危機感を共有し誕生した。
連携の基本は「協力」「共有」「分担」の3つの柱にある。具体的な取り組みとして、高額なコンピューター診断機などの機材や部品の仕入れを共有し、コスト削減と技術対応力の向上を図っている。また、各社の定休日を分散設定することで、日曜・祝日であっても必ずどこかの店舗が営業している体制を構築し、さらにロードサービス体制を協力体制とし、事故現場から最寄りの店が迅速に駆けつけることができる仕組みを整えている。これにより、顧客がトラブルに遭遇している時間を極力少なくすることを可能にした。
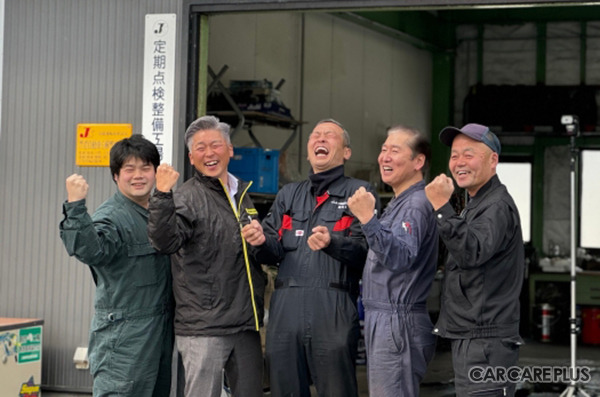
特化分野の開拓による事業継承の成功
コトモビの成功事例の中でも特に注目されるのが、グループ企業である「なにわ自動車」における事業継承と電子制御装置整備事業への進出である。同社は2023年10月に義理の息子である浪花直也氏を迎え入れ、2024年1月には特定整備事業の認証を取得した。
直也氏は入社前、「この変化していく自動車業界で、夫婦や家族経営の小さな整備工場が本当に生き残っていけるのか」というネガティブな不安を抱えていた。さらに、元々義父が好きで来ていた既存の顧客が、自身に代替わりした後もそのまま残ってくれるのかという不安があったため、当初は「継ぎたい」と自ら口にすることができなかったという。
しかし、この「ピンチ」を「チャンス」と捉え、自動車業界がどう変化しても「タイヤとガラスは当分変化がないだろう」と直感。電子制御装置整備(ADAS対応)の重要性の高まりを見据えたこの分野への特化をビジネスチャンスと判断し、ガラス交換・修理、エーミング、四輪アライメント調整といった新規事業を立ち上げた。
これは、OBD検査対象車の増加に伴う電子制御装置整備の重要性の高まりを捉えた戦略的な一手であり、グループ内で不足していた専門サービス(ガラス交換やエーミングなど)を内製化し、町内で完結できる仕組みを実現した。実際、新規事業の立ち上げ後、エーミング単体での依頼は前年比で17件増となるなど、グループ内での分業・受発注が着実に成果を上げている。

「町おこし」に貢献するモビリティ展開とイベント
コトモビは、自動車整備の枠を超え、地域社会への貢献を積極的に行っている。11月9日には、「車離れ」が進む若者に興味を持ってもらうことを目的に、県内では初となる軽オープンカー「コペン」のオーナーを集めた「コペンミーティング」を主催した。各地(兵庫県や香川県)から集まった参加者が、琴浦町の自然や食を満喫するドライブを楽しみ、地域外からの集客と交流を生み出した。コトモビは、レンタカー事業においても「非日常」を体感できる「コペン」を提供している。
ちなみに、コトモビ事務局を務める出崎氏(赤碕ダイハツ)と琴浦町を結びつけたのもコペンであった。広島大学出身でドライブが大好きな出崎氏は、大学時代に4回も赤碕ダイハツのコペンレンタカーを利用した末、琴浦町の魅力に惹かれ就職を決意している。出崎氏は、都会では得られにくい、野菜を毎日もらうような「人間本来の温かみ」をこの地域で実感したことが決め手となったと話す。このように、「コペン」という車が、若者を地域に誘致し、グループの事務局という重要な役割を担う人材を呼び込む「奇跡的な誘致」につながっている。

セミナーでの注目度と成功要因
このコトモビの事例は、業界関係者向けのセミナーでも「非常に珍しい連携事例」として、大きな注目を集めている。特に、人口が減少している「田舎」において、事業継承と新たなビジネスモデル確立を両立させたことは「奇跡」に近い成功と評価されている。
成功要因は、単に協力することではなく、各社が重複を避け、専門分野を分担した点にある。全員が同じように中古車販売や車検に注力するのではなく、なにわ自動車が電子制御装置整備分野に特化し、他のグループ企業(ダイハツ、ホンダ、スズキの看板を持つ店がある)が、それぞれの得意分野(純正スキャンツールの知見など)を活かして連携することで、高度化する自動車技術にグループ全体で対応できる体制を構築した。事務局の出崎氏は、メンバー間の意見の対立や連絡の難しさといった運営上の課題を抱えながらも、グループの目標達成のために奔走し、この連携体を支えている。

人口減少と技術進化が同時進行する自動車アフターマーケット業界において、個社単独で生き残ることは困難であり、地域連携は有効な手立てである。コトモビの事例は、連携の真価が「差異化」と「戦略的投資」にあることを示唆している。
特に、電子制御装置整備やOBD検査といった次世代整備への対応が不可避となる中、高額な純正スキャンツールや特殊な設備を全ての事業者が揃えることは非現実的である。コトモビのように、グループ内で役割を分担し、誰がどのリソース(設備、技術、知識)を提供するかを明確にすることで、地域のお客様のモビリティを永続的に守る受け皿となることが可能となる。






